【特集】熱中症対策・予防について
【特集】熱中症対策・予防について
熱中症とは?
熱中症とは、高温多湿な環境下で体温調節がうまくできなくなり、体内の水分や塩分のバランスが崩れることで発生する症状の総称です。軽度の場合はめまいや立ちくらみが起こりますが、重症になると意識障害やけいれんを引き起こし、命に関わる危険性もあります。特に近年の気温上昇により、より注意が必要な状況になっています。本特集では、熱中症のリスクや予防策、おすすめの対策商品について詳しく解説します。

1.昔と違う!?近年の気象環境にあわせた熱中対策、予防商品のご提案

2024年、日本の平均気温基準値(1991~2020年平均値)からの偏差は+1.48℃で、統計開始以降、最も高い値を更新。日本の年平均気温は、様々な変動を繰り返しながら上昇しており、長期的には100年あたり1.40℃の割合で上昇しています。特に1990年代以降、高温となる年が頻出しています。
国土交通省 気象庁の公式サイトより抜粋→リンクはこちら
おすすめの対策商品
2.熱中症のしくみ

熱中症を引き起こす条件は、「環境」と「からだ」と「行動」によるものが考えられます。
「環境」の要因は、気温が高い、湿度が高い、風が弱いなどがあります。
「からだ」の要因は、激しい労働や運動によって体内に著しい熱が生じたり、暑い環境に体が十分に対応できないことなどがあります。
人間の身体は、平常時は体温が上がっても汗や皮膚温度が上昇することで体温が外へ逃げる仕組みとなっており、体温調節が自然と行われます
熱中症とは、高温多湿な環境で体温調節機能がうまく働かず、体に熱がこもった状態です。特に臓器の温度である深部体温が上がりすぎると、危険な状態になります。
環境省の公式サイトより抜粋→リンクはこちら
3.熱中症の種類
熱中症の症状と分類(『日本救急医学会熱中症分類2015』より)
| 症状 | 重症度 | 治療 | 臨床症状からの分類 | |
|---|---|---|---|---|
Ⅰ度(応急処置と見守り) |
めまい、立ちくらみ、生あくび、大量の発汗 筋肉痛、筋肉の硬直(こむら返り) 意識障害を認めない(JCS=0) |
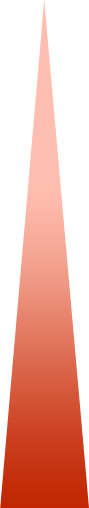 |
通常は現場で対応可能
→冷所での安静、体表冷却、水分とNa補給 |
熱けいれん、熱失神 ※改善が見られれば応急処置でOK I度の症状が徐々に改善している場合のみ、現場の応急処置と見守りでOK |
Ⅱ度(医療機関へ) |
頭痛、嘔吐、 倦怠感、虚脱感、 集中力や判断力の低下 (JCS≦1) |
医療機関で診療が必要
→体温管理、安静、水分・Na補給(点滴含む) |
熱疲労 ※改善が見られない場合は病院へ搬送 Ⅱ度の症状が出現したり、I度に改善が見られない場合、すぐ病院へ搬送する(周囲の人が判断) |
|
Ⅲ度(入院加療) |
下下記の3つのうちいずれかを含む
(C)中枢神経症状(意識障害JCS≧2、小脳症状、痙攣発作)(H/K)肝・腎機能障害(入院経過観察、入院加療が必要な程度の肝または腎障害) (D)血液凝固異常(急性期DIC診断基準(日本救急医学会)にてDICと診断)⇒Ⅲ度の中でも重症型 |
入院加療(場合により集中治療)が必要
→体温管理(体表冷却に加え体内冷却、血管内冷却などを追加)呼吸、循環管理DIC治療 |
熱射病 ※救急隊や病院で診断 Ⅲ度か否かは救急隊員や、病院到着後の診療・検査により診断される |
厚生労働省の公式サイトより抜粋→リンクはこちら
5.熱中症予防 FAQ
Q-1.熱中症対策について法律に位置づけられたと聞きました。どのようなことが定められたのですか。
●近年、熱中症による救急搬送人員は毎年数万人を超え、死亡者数も毎年1,000人を超える状況となっています。これらを背景として、熱中症対策を一層推進するため、令和5年4月、第211回国会において、気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律(令和5年法律第23号。以下「改正法」といいます。)が可決・成立し、令和6年4月から全面施行されました。
●改正法の主なポイントは以下の5点です。
①政府一体となった熱中症対策の推進を図るため、政府が「熱中症対策実行計画」を定めるようにすること。
※政府の熱中症対策実行計画は、令和5年5月30日に閣議決定済みです。
②環境省が気象庁と共同で運用する「熱中症警戒アラート」を「熱中症警戒情報」として法律に位置づけるとともに、今後起こり得る極端な高温の発生を見据え、一段上の「熱中症特別警戒情報」を創設すること
③市区町村長が、暑さをしのげる市区町村内の施設を「指定暑熱避難施設」として指定できるようにすること
④市区町村長が、熱中症対策の普及啓発等に取り組む団体を「熱中症対策普及団体」として指定できるようにすること
⑤独立行政法人環境再生保全機構の業務として、熱中症警戒情報等の発表の前提となる情報の整理・分析等の業務や、地域における熱中症対策の推進に関する情報の収集・提供等の業務を追加すること
Q-2.熱中症対策実行計画とは何ですか。
●気候変動適応法第16条の規定に基づいて定められた、政府の熱中症対策に関する計画が「熱中症対策実行計画」(以下「実行計画」といいます。)です。この実行計画は、令和5年5月30日に閣議決定されています。
●実行計画では、
・2030年度までに、「熱中症による死亡者数を現状から半減する」ことを目標としています
・以下の8つの柱とする熱中症対策の具体的な施策を講じることとしています。
①命と健康を守るための普及啓発及び情報提供
②高齢者、こども等の熱中症弱者のための熱中症対策
③管理者がいる場等における熱中症対策
④地方公共団体及び地域の関係主体における熱中症対策
⑤産業界との連携
⑥熱中症対策の調査研究の推進
⑦極端な高温の発生への備え
⑧熱中症特別警戒情報の発表・周知と迅速な対策の実施
●この実行計画に基づき、関係府省庁が連携して熱中症対策に取り組んでいます。
Q-3.熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報とは何ですか。
●政府では、熱中症による健康被害が生じるおそれがある場合には気候変動適応法第18条に基づき「熱中症警戒情報」を、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある場合には同法第19条第1項の基づき「熱中症特別警戒情報」を発表し、国民の皆様へ熱中症を予防するための行動をとるよう呼びかけを行います。
これらはいずれも、「熱中症特別警戒情報等の運用に関する指針」(令和6年2月27日環境省大臣官房環境保健部)に基づいて運用しています。
●熱中症警戒情報は、
・熱中症による人の健康に係る被害が生ずるおそれがある場合に発表します。
・具体的には、予報区内の暑さ指数(WBGT)の情報提供を行っているいずれかの地点※において、暑さ指数(WBGT)の最高値が33以上(小数点以下の端数を四捨五入した値)となることが予測される場合に発表します。
※暑さ指数(WBGT)は、全国841地点(令和6年6月時点)で算出しています。
・発表単位は、全国を58の地域に区分した予報区です。
・対象日の前日午後5時頃及び当日午前5時頃に発表します。
・令和5年度における延べ発表回数は1,232回です。
・通称は「熱中症警戒アラート」です。
●熱中症特別警戒情報は、
・熱中症による人の健康に係る重大な被害が生ずるおそれがある場合に発表します。
・具体的には、原則、都道府県内の暑さ指数(WBGT)の情報提供を行っている全ての地点において、暑さ指数(WBGT)の最高値が35以上(小数点以下の端数を四捨五入した値)となることが予測される場合に発表します。
・発表単位は、都道府県です。
・対象日の前日午前10時頃の予測値で判断し、前日午後2時頃に発表します。
・通称は「熱中症特別警戒アラート」です。
Q-4.熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報が発表されたら、どのように知らされるのですか。
●熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報とも、その発表に関する情報は、環境省熱中症予防情報サイト、LINEの環境省アカウント、メール配信サービス等により発信を行います。また、熱中症特別警戒情報は、これに加えて報道発表等も行う予定です。
●熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報の発表に関する情報については、環境省を含む関係府省庁だけでなく、報道機関の協力も得ながら、広く国民の皆様にお伝えし、熱中症予防行動の呼びかけを行います。
Q-5.「暑さ指数(WBGT)」とは何ですか。。
●暑さ指数(WBGT)は、人体と外気との熱のやり取り(熱収支)に着目し、気温、湿度、日射・輻射(ふくしゃ)、風の要素を基に算出する指標です。
【算出式】
暑さ指数(WBGT)=0.7×湿球温度+0.2×黒球温度+0.1×乾球温度
・乾球温度:通常の温度計が示す温度。いわゆる気温のこと。
・湿球温度:湿度が低いほど水分の蒸発により気化熱が大きくなることを利用した、空気の湿り具合を示す温度。湿球温度は湿度が高いときに乾球温度に近づき、湿度が低いときに低くなる。
・黒球温度:黒色に塗装した中空の銅球で計測した温度。日射や高温化した路面からの輻射熱の強さ等により、黒球温度は高くなる。
Q-6.気温ではなく「暑さ指数(WBGT)」を使うのはなぜですか。
●熱中症の発生と気象条件(温度のほか、湿度、風、日射・輻射など)の間には密接な関係があります。
●例えば、気温が高い日は体内にたまった熱を体外に逃しにくくなります。また、湿度が高い場合、無風である場合なども同様です。日射・輻射などが強い場合は、体温の上昇につながります。
●実際に、熱中症で救急搬送される人の数は、気温のみの場合よりも、気温に加え、湿度や日射・輻射を考慮する暑さ指数(WBGT)を用いた場合の方がより関連していることが知られています。こういったことから、政府では、熱中症リスクを表す際に、暑さ指数(WBGT)を使用しています。
Q-7.熱中症警戒情報、熱中症特別警戒情報が発表された場合には、どのような行動をとるべきですか。熱中症予防行動とは何ですか。
●熱中症は、死亡する可能性のある病態です。一方で、適切な熱中症予防行動を知って、それを実行することで、防ぐことができる病態でもあります。
●熱中症予防行動とは、熱中症の予防につながる行動のことであり、具体的には、以下のような行動が挙げられます。
・暑さ指数(WBGT)の確認
・身近な人の見守り・声かけ
・適切なエアコンの使用
・こまめな水分・塩分の補給 など
●熱中症警戒情報や熱中症特別警戒情報の発表時には、こうした熱中症予防行動をとることが重要です。
●また、特に、熱中症による重大な健康被害が生じるおそれがある「熱中症特別警戒情報」の対象地域にお住まいの方々には、
・涼しい環境で過ごす
・熱中症にかかりやすい高齢者、乳幼児等が、エアコン等のある涼しい環境で過ごせているかを確認する
・学校や会社、イベント等の管理者は、全ての方が熱中症対策を徹底できているかを確認し、徹底できていない場合には、運動、外出、イベント等の中止、延期、変更や、リモートワークへの切り替え等を判断いただくなど、熱中症予防行動の徹底をお願いします。
Q-8.Q:2025年6月1日から施行の熱中症対策、義務化の条件は?
★作業環境
・暑さ指数(WBGT)が28度以上、または気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または1日4時間以上の作業が想定される環境
★報告体制
・熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、報告できる体制を整備
・迅速に連絡できる体制を確立
★手順の作成
・初期症状を認識し、応急措置や医療機関への搬送、体調急変時等に対処する手順を作成
・関係者にマニュアルなどで周知
★関係者への周知
・対策の目的や手順、連絡体制を関係者に周知し、理解を促す
・従業員への教育や説明会などを実施することも効果的
環境省の公式サイトより抜粋→リンクはこちら

メールでお問合せ
お電話でのお問合せ
| 本社(香川) | 087-802-7272 |
| 山陰オフィス | 0853-27-9845 |
| 東京オフィス | 03-6428-6544 |
| 大阪オフィス | 06-6379-5330 |







